学級経営をイチから学び直そうと思いました。
動機については、以下の記事に書いています。

とりあえず、学級経営に関する本を5冊読んでみる企画。
第4弾はこの本を読んでみました。
参考・引用文献は以下の通りです。
村松英治・相馬亨(2017)
「学びに向かう力」を鍛える学級づくり
東洋館出版社
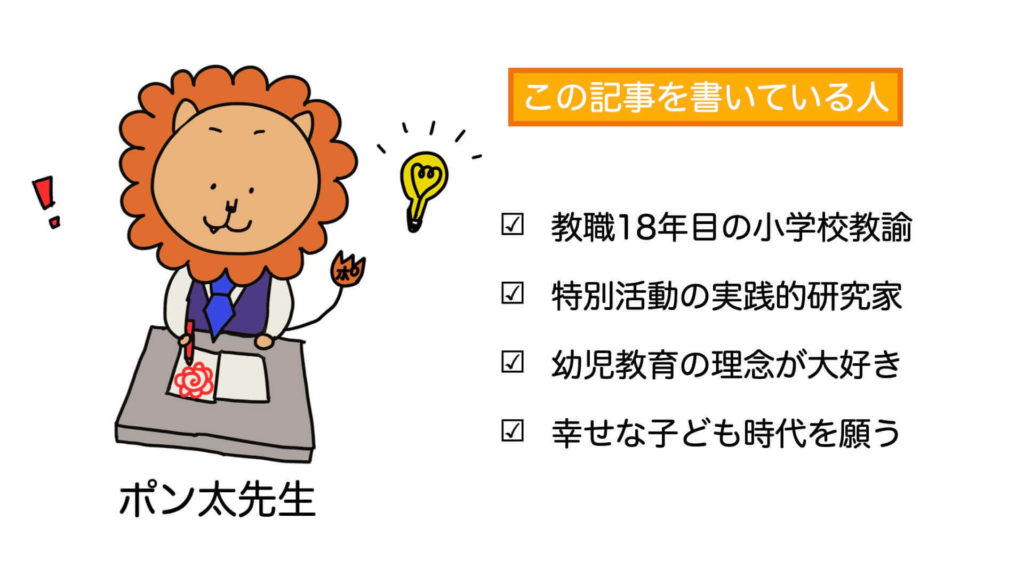
全体の印象
まず驚いたのは、著者のお2人は、まだかなりお若いのであろうな…ということです(違っていたらすみません)。
この若さで、この力量…
圧倒されました。
2人の先生方の凝縮された実践が、惜しげも無く語られていました。
本の内容もさることながら、何よりもお2人の熱量に刺激を受けました。
こんなにも熱く、ひたむきに教育と向き合っている先生がいるのだな、という感動。
そして、本を読み進めていくと、同じように熱量の高い先生方と共に、切磋琢磨して、技を磨いているお2人の様子が伝わってきました。
純粋に
「私も、がんばらなくては!」
という刺激を受けました。
今回の記事でも、私が今後の実践に生かしていくこと、大切にしたいことだけを厳選して、書き残したいと思います。
正直、本の内容を全てまとめたいくらいですが…
そういうわけにもいかないので。
この記事は
「私のアウトプットと記録」
のために書いていますので、あしからず。
私と同じように、学級経営に悩む先生方にとって、
少しでもこの記事が参考になれば、幸いです。
学びに向かう力
「学びに向かう力」
と聞くと、どのような力を思い浮かべますか?
「くじけない心」
「やり抜く力」
のような力を、思い浮かべる方もいるかもしれません。
この本の中で語られる「学びに向かう力」は、
子どもの「やりたい!学びたい!」を引き出す
もしくは、大切にする
といった捉えに感じました。
素敵ですよね。
おしゃべりタイム
子どもたちは、「発言」だと尻込みしますが、「おしゃべり」だと夢中になるのです。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p17
授業の中で
「お隣の人と話してみて」
という場面は多いと思います。
これを、「おしゃべりタイム」としてみる実践です。
聞いただけでも楽しそうですよね。
松村先生は、そこからさらに、おしゃべりタイムについて詳しく説明しています。
1 おしゃべりタイムの視点
□ 誰とおしゃべりさせるか
2人(お隣と)or 3〜4人(近くの友達と)
□ 何のためにおしゃべりするか
・ペアでたくさんのアイディアを出す
・理解しているかを確認し合う…など
2 おしゃべりタイムを挟むタイミング
「いつでも」「どこでも」「何度でも」
特に、教師の説明が多くなりそうな授業では、5分おきに挟みます。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p18-21から抜粋
「おしゃべりタイム」を行うことの意義は、教室にいる全員の子どもたちが、自信とワクワク感をもって自分の考えをアウトプットする場をつくることにあります。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p21
ネーミングを工夫して、目的意識を明確にして取り組むことで、同じような実践でも、効果は全然違うのだろうな、と感じました。
「楽しい」ということ
楽しさは、その瞬間の味わいだけではなく、学びに向かう力の源泉なのかもしれません。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p44
これは、特に1年生には大切なことだと思いました。
いや、きっとどの学年でもそうです。
学ぶことって、まずは
「楽しい」
と思えないと、主体的に学べないですよね。
「学びに向かう力」
もきっと、この「楽しい」が土台になる気がします。
本の中で松村先生は、「楽しい」の正体について書いています。
1 知的好奇心による「楽しい」
2 自己選択・自己決定による「楽しい」
3 ユーモアによる「楽しい」
どうでしょうか?
この3つが全てできる先生は、かなり凄いと思います。
先生によって、得意としている「楽しい」がありそうです。
私は、2の自己選択・自己決定による「楽しい」が得意かもしれません。
知的好奇心は…
もっと教材研究や授業をがんばらないとなぁ…と反省しました。
ユーモアは…
正直苦手、という感じです。
しかし、こうして「楽しい」の正体が見えたわけですから、
今後は3つともがんばるぞ!という気持ちになれました。
授業について
振り返り
毎時間の習慣にする
これは、わかっていても、なぜか手薄になる部分ではないでしょうか。
自戒をこめて、書き留めたいと思いました。
本の中では、かなり詳しく習慣化の方法が書いてありました。
ぜひ、ご自分でも読んでみてください。
めあてや見通しを意識させる
「授業の最後に、学習のめあてや見通しに基づいて振り返る」ことを、授業のはじめに伝えておくことが、とても大切だと思います。授業の最後になってから「振り返りを書きましょう」と促すだけでは、むずかしいのではないかと思うからです。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p49
これは、「当たり前だよね」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、この振り返りの方法を実践するためには、
「子どもにとって、学習のめあてや見通しが明確な授業をする」
ことが大前提です。
子どもがめあてや見通しを意識できるような授業を、毎時間するというのは、「言うは易し、行うは難し」だと思います。
「黒板に毎時間めあてを書いている」という事ではありません。
著者が、常に質の高い授業をしていることが垣間見えました。
具体的な視点を示す
著者は、5つの視点を示しています。
① たいせつだとおもったこと
② わかったこと・できたこと
③ わかりかた・できかた
④ よくわからなかったこと
⑤ もっとやりたいこと
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p51
1年生にもわかる言葉で書いていることが、すごくありがたいです。
もちろん、この5つの視点を全て書くのではなく、1つだけ選ぶ子もいれば、参考程度にして自分で好きなように書く子もいるそうです。
ワーキングメモリ
本の中で、「指示が通りにくい子ども」についての、エピソードが書かれていました。
それは、その子どもが「不真面目」であったり、「ふざけ」たりしているのではなく、ワーキングメモリ(短時間に頭の中で情報を保持し、操作する能力)のせいではないか、ということが書かれていました。
もしかして、その子は、情報を処理する作業場が、人よりも狭いのではないか?(ワーキングメモリが小さいのではないか?)と考えるようになったのです。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p80
相馬先生は、子どもたちが次の活動(行動)への見通しを「見える化」することで、ワーキングメモリの負担を減らすことができる、と述べています。
本の中で、以下のような「見える化」が紹介されていました。
○ 教室に学習計画を掲示する
○ 教室に本時の流れを掲示する(授業の流れはある程度固定する)
○ 黒板は本時に必要なものだけ掲示する
○ モデルを示す(話し方・聞き方・交流の仕方・作品の例など)
○ 困った時の約束をする
○ 机の上は必要なものだけ置く約束をする
○ 付箋を使ってやることリストを作成する
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p82
中でも、
「困った時にどうするかを約束の形で学級で決めておく」
(支援を求める仕組みをつくる)
ことは、効果があったそうです。
なるほど!と感じました。
「学級がなかなか落ち着かない」
という前に、先生にできることがたくさんあるのだなぁと、反省しました。
授業規律
本の中で、
「授業規律を考える上での3つの視点」
がありましたので、まとめます。
1「誰のためにあるのか」
授業規律は、子どもと共につくられることが必要
2「何のためにあるのか」
子どもたち自身、学級全体が成長するためにある
【わからないことに出会ったとき】
① わからないことを告白・相談する
② 告白・相談された友達は全力で協力する
③ それでもわからなかったら、さらに別な友達に相談する
④わかったことを友達に説明する
3 「いつ、つくるのか」
4月、特に最初の1週間が、授業規律のつくりどき
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p125-126から抜粋
かなり簡単にまとめていますので、興味がある方はぜひ、実際に本を読んでみてください。
授業規律は、
「先生の仕事を楽にするためのもの」
ではなく
「子どもがよりよく学ぶためのもの」
という視点に立つことが、何よりも大切だと再認識しました。
このとき、気をつけなければならないことがあります。それは、「子どもとゼロから授業規律をつくるわけではない」ということです。まずは、目の前の子どもたちがどのような個性をもっているのかを見渡し、それらが最も良い形で発露する姿をイメージした上で、教師がよいと考えることや身につけさせたいことを土台にします。〜中略〜
互いの納得が得られた授業規律は、子供を縛るのではなく、むしろ解放してくれます。
村松英治・相馬亨(2017)「『学びに向かう力』を鍛える学級づくり」東洋館出版社 p127-128
やはり、先生が丸腰ではダメということですね。
先生には、学級が育つ見通しや、イメージがないといけません。
そこは、がんばって考える必要がありますね。
終わりに
記事では取り上げませんでしたが、この本の最後の章には
「仲間と学び合い授業を磨く」
ということが書いてありました。
正直、この章の熱量が、一番高かったように感じました。
今回の趣旨からはそれるので、あえて書きませんでしたが、先生をしている人にはぜひ読んでほしいと感じる内容でした。
今回も、多くの学びがありました。
たくさんのエネルギーを得られた1冊だったと思います。
多くのご示唆をくださった、松村先生、相馬先生に感謝です。
ありがとうございました。









